新型コロナウイルス:専門家が政府に提言-日本版CDCの創設や、医療コンテナ導入を
感染拡大は日本を襲った大災害
同戦略会議は2月中旬、国民に向け、感染症対策を意識した“新生活習慣”を身に付けてもらおうと緊急提言した。今回は感染拡大が深刻化する中で、政府がとるべき今後の感染症対策をまとめた。新型コロナウイルスによる感染拡大を「日本を襲った大災害」ととらえ、将来も起きるであろう感染症に立ち向かうため、以下の項目を政府に提言する予定だ。
(1)医療体制、専門家チーム体制、意思決定系統などの見直し
新型コロナウイルスの感染源は中国・武漢の市場の野生動物との説もあったが、まだ正確には特定されていない。今後も再び発生する可能性があり、それがまた今回のように世界中に感染拡大する。私たち日本人は「感染症はいつでも、どこでも起こりうる」という意識を持たなければならない。
感染症危機管理システムを構築する必要があり、感染症だけの専門家ではなく、情報学や、免疫学など幅広い分野の人を集めた専門家チームを結成し、政府に提言する仕組みを作る。
米国のCDCは人員が1万数千人、年間予算8000億円を超え、情報収集、国民への説明、検疫作業まで幅広く行っている。これに対し、日本の国立感染症研究所は人員が約300人、予算が約80億円と大きな差がある。感染症危機管理の司令塔となり、人材や施設の充実したCDCを手本とした新組織の立ち上げを急ぐ。
(2)感染症検査態勢・検疫態勢の拡大と仕組みの再構築
新型コロナウイルスでは、無症状感染者の特定ができていないため、国内での感染源・感染ルートが分からない感染が拡大している。このため、感染者を早期に特定するための医療機関を拡大すべきだ。
新しい感染症を検査できる技術や設備があっても、保険適用の枠組みがないと、病院の費用負担で検査しなくてならない。感染しているかを判定する検査キットや機器の設置、人員の配置を含めた仕組みを作っていく。
(3)平時も利用可能な「医療コンテナ」の導入
新型コロナウイルスに感染した疑いのある人の診察は、現在、一般の患者への感染を防ぐため、病院の敷地の隅にあるプレハブ小屋などで行われているケースも少なくない。
医療コンテナの設備は、病院と隔離できるので、院内にウイルスを持ち込むリスクを低減できる。ウイルスがあるかもしれない「レッドゾーン」と安全区域の「グリーンゾーン」の区別が容易なので、通常の外来と、感染者外来の診療がそれぞれ継続可能になる。
エックス線装置やCT(コンピューター断層撮影装置)を搭載したコンテナとの連結により、院内の施設が汚染されることなく使うことも可能となる。移動式コンテナは緊急時に必要な場所に移動・設置が可能なので、平時から医療コンテナを使っていれば、緊急時にも活用できる。
(4)有事処方制度の導入と、平時からの情報システムの構築
現行のお薬手帳などによる管理では、ポリファーマシー(多くの薬を服用して副作用など有害なことが起きること)の評価や、処方されている薬の優先順位や中止の基準が明確でない。災害時は薬の管理が難しくなり、慢性疾患が悪化するなどして、災害関連死につながることが想定される。
今回の新型コロナウイルス感染でも、風邪症状がない高齢者や基礎疾患がある人が持病薬をもらうとき、感染リスクが高い人が来院しなくても済む体制を整えることが課題となっている。
こうしたことを踏まえて、お薬手帳に代わって、マイナンバーなどを活用した「電子お薬手帳」による情報管理システムを導入すべきだ。また、災害時や、今回の感染症拡大時のような有事の際に効果的な臨時処方(7日分程度)を事前に行っておくようにする。こうしておけば、もし感染症で隔離されることになっても、必要な薬の提供を受けることが可能になる。
(5)感染症BCPの策定と、テレワークの加速度的な導入促進
感染症対策は、まさに災害対策と同じように国土強靱(きょうじん)化政策(国民の生命と財産を守り抜くため、事前防災・減災の考えに基づき、強くてしなやかな国をつくる)に位置付けるべきだ。
BCP(事業継続計画)は、企業などが災害、テロ攻撃などの緊急事態に、被害を最小限に抑えて、事業の継続や復旧を図る計画。企業だけでなく、あらゆる組織は、災害BCPと同様に、今回のような感染症拡大時のための「感染症BCP」を策定しておく必要がある。
また、出社しないで自宅などで勤務する「テレワーク」は、今回だけの一過性の取り組みに終わらせないで、継続的な国民運動にしていくべきだ。今後も感染症問題が起きた時や災害時に、テレワークが必ず役立つ。
(6)学校、職場、交通機関、イベントなど大勢の人が集まる所の環境消毒習慣の徹底
多くの人が集まる(マスギャザリング)場所では、除菌など環境消毒を行うことが、感染症拡大の対策として効果的である。しかし、人手不足や、コストがかかるので、徹底できていないのが現状だ。今回、多くの感染者を出し、大きな問題となった豪華クルーズ船は、艦内の環境衛生を守るのが本当に難しかった。
米国の病院では、院内感染を防ぐため、紫外線殺菌ロボットが院内を回っている。人の手による清掃では限界があるので、薬に耐性のある細菌を退治する紫外線を放つロボットが活躍している。
除菌性が持続する除菌剤を活用することで、頻繫に消毒しなくても、学校でインフルエンザ感染の子どもを大幅に減らせることが分かっている。最新技術を使って、環境消毒ができる技術や商品の周知も重要だ。
(7)国民一人一人が「7つの約束」(感染症に対する心得)の実行と順守を
感染症を「正しく恐れる」など、日常生活での7項目の約束を国民に求める。これは先に、この戦略会議が2月10日に発表したもの。
17年ぶりの政界汚職捜査を進める東京地検特捜部:「最強の捜査機関」の歴史

戦後間もない「昭電疑獄」がきっかけで特捜部誕生
事件の捜査は通常、最初に警察が行う。容疑者は逮捕・検挙の後、検察庁に送られ、検察官は起訴するか、罪を問わない不起訴にするか判断。起訴になって裁判が始まると、検察官は裁判に立ち会い、被告人の有罪を証明していく。簡単に言うと、警察が犯罪の捜査、検察が公判維持(裁判での立証)と職務が分かれている。
だが、政治家や高級官僚がからむ汚職、大型経済犯罪(商法の特別背任事件など)といった難事件は、東京、大阪、名古屋の各地方検察庁に設置された特捜部が捜査する。刑事訴訟法191条1項の「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる」と、検察庁法6条の「検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる」の規定に基づいている。
東京地検特捜部は、終戦から4年後の1949年5月に発足した。源流は47年に同地検に設置された「隠退蔵物資事件捜査部」だ。当時は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下で、戦後の混乱で隠されていた旧陸海軍や政府の物資に関する事件を担当した。
翌48年、食糧増産政策に関する巨額の復興資金を受けた肥料メーカー「昭和電工」から、政界・官界に賄賂が贈られた汚職事件「昭電疑獄」が起きた。当時の芦田均内閣は、この事件で西尾末広副総理が東京地検に逮捕され、倒れた。芦田首相本人も総辞職から2カ月後に逮捕される大事件となった。
この事件がきっかけとなり、捜査終結後に担当した検事と、隠退蔵物資事件捜査部、さらに全国から選ばれた検事が合体して、東京地検特捜部が誕生したのである。ただ、昭電疑獄は裁判になって芦田、西尾、大蔵省の福田赳夫主計局長(後に首相)ら主だった被告が、職務権限などの法律解釈で無罪となった。
佐藤栄作幹事長の逮捕直前に指揮権発動の「造船疑獄」
東京地検特捜部が陣容を整え、正式に政界と対決したのは、占領が解除となり、主権を回復してから2年後の1954年に起きた「造船疑獄」だ。国家助成による計画造船の割り当てを巡り、海運・造船会社から政界の実力者に金銭が広くばらまかれた。
特捜部は会社社長や、政治家を次々と逮捕。そして、当時の吉田茂長期政権を支える与党・自由党の佐藤栄作幹事長(後に首相)の逮捕状請求の許可を、検察トップの検事総長が犬養健法相に求めた時に前代未聞の「指揮権発動」(検察庁法14条により、法相は検事総長を指揮できる)があった。次に池田勇人総務会長(後に首相)の逮捕も予定されており、2人が逮捕されれば内閣が崩壊するのは間違いなかった。吉田首相らの指示で法相が「佐藤逮捕」に待ったをかけ、事件捜査は崩れた。
しかし、法相は翌日に辞職。吉田内閣の支持率は低下し、その年に通算6年半続いた長期政権は倒れ、ワンマン宰相は退陣した。この事件も、裁判になると多くの被告が無罪となった。
「総理の犯罪」と闘ったロッキード事件
検察が政界捜査で全面勝利となったのは、1976年、「総理大臣の犯罪」と闘った「ロッキード事件」だ。全日空の旅客機導入の選定に絡み、米航空機メーカーのロッキード社の販売代理店となった商社「丸紅」などから、田中角栄元首相ら政治家に多額の賄賂が流れた。米国上院外交委員会で発覚し、東京地検特捜部は米国の資料などを徹底的に分析。秘密資金の流れをつかんで、田中元首相、橋本登美三郎元運輸大臣ら3人の政治家を逮捕した。
捜査開始の検察首脳会議で、布施健検事総長は「日米両国にまたがる事件だから、真相解明には困難が多いだろうが、検察が失敗を恐れて消極的な態度を取ることは許されない」「責任はすべて私がとる。思う存分、捜査をやってほしい」と検察の並々ならぬ決意を述べた。
政治家逮捕前の自民党内では、捜査を容認している三木武夫首相を早く退陣させようという「三木おろし」の工作があった。稲葉修法相は電話で法務省刑事局長から田中逮捕の許可を求められ、「(検察を)信頼しましょう」と異論をはさまなかった。こうして、造船疑獄の時のような指揮権発動はなく、事件捜査は進んだ。
5億円の賄賂を受け取り、受託収賄罪に問われた田中元首相に対し、東京地裁は1983年、検察側の主張を認め、懲役4年、追徴金5億円の実刑判決を言い渡した。元首相は最高裁に上告中の93年に死亡したが、贈賄側の丸紅元社長らの有罪が95年に最高裁で確定し、検察が勝った。だが特捜部を含めて検察は、ロッキード裁判対策に人材を割かれ、捜査態勢が弱くなったことを否定できず、80年代はしばらく政界捜査が途絶えた。
リクルート事件で総辞職した竹下内閣
ロッキード事件の後、東京地検特捜部が再び世間の注目を集めたのは、1988年に発覚した「リクルート事件」だ。就職情報誌から事業を拡大して急成長中だったリクルート社が、子会社の未公開株を政界などにばらまいた。政治家では中曽根康弘内閣の藤波孝生元官房長官と当時野党だった公明党の衆院議員が起訴された。
特捜部の捜査が進む中、当時の竹下登内閣でリクルート社と関係した宮沢喜一蔵相(後に首相)ら閣僚が次々と辞任。昭和から平成に代わり、89年5月には国会で中曽根元首相の証人喚問が行われた。竹下首相が公表していなかったリクルート社からの借入金が明らかとなり、国民の政治不信から支持率が10%を割った竹下内閣は、翌6月、総辞職した。
特捜検察の怖さを知らない今の政治家たち
特捜部出身の検事総長は多い。その1人で、「ミスター検察」と呼ばれた伊藤栄樹元検事総長は1985年の就任時、検事たちに「巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな」と訓示した。
時に政権・与党に立ち向かう「最強の捜査機関」はリクルート事件の後、散発的に政治家の逮捕・起訴を重ねたが、21世紀に入り大型の政界汚職事件から17年も遠ざかっていた。
長い空白期間のためか、今回のIR事件では、贈収賄側双方の大胆な金銭(賄賂)の授受が疑われる状況になっている。贈賄罪で起訴された中国企業の元顧問は、収賄罪で起訴された秋元司衆院議員(元IR担当内閣府副大臣、自民党を離党)ら政治家に金銭を渡したとされる時期に、大量の札束を指さす自身の写真をフェイスブックに投稿したと報じられるほどだ。現在の政治家たちは「東京地検特捜部の怖さを知らないからだ」と指摘する法務関係者もいる。
「検察ファッショ」「人質司法」の批判も
特捜の捜査に対しては、昔から「検察ファッショ」という批判がある。事件史で見たように、無罪となるケースもあり、初めは多くの逮捕者を出したのに竜頭蛇尾で終わることもあったからだ。検察当局が勝手に事件の構図を描いて暴走していると、強権的な捜査が批判されるのだ。
大阪地検特捜部では2010年、厚労省の村木厚子局長(無罪確定後に事務次官)に対する虚偽公文書作成容疑などの捜査で、主任検事が証拠物件のフロッピーディスクを改ざんする事件があった。特捜部長(当時)らがこのことを隠したとして犯人隠避の容疑で逮捕され、検事総長が辞任して検察の権威は失墜した。「特捜部不要論」が出てきて、東京地検特捜部も捜査態勢が一部縮小された。こうしたことが、大型事件から遠ざかる要因の一つになった。
特捜部は政界以外に経済事件も捜査する。現在、海外逃亡で世界的に注目されている日産自動車のカルロス・ゴーン会長(当時)を巨額の役員報酬を隠したなどとして、東京地検は2018年に逮捕・起訴した。
ゴーン被告は、130日間、東京拘置所に収容されたことで、否認すれば長期間、外に出られない「人質司法」だと日本の刑事司法制度を批判している。被告は1月8日、レバノンでの記者会見で、「(特捜部の取り調べは)1日8時間にも及び、弁護士の立ち会いがなく、自白を強要された」などの主張を述べた。一方、東京地検は「1日平均4時間弱。弁護士とは日曜以外は2時間前後、接見していた」と直ちに反論した。
特捜部の捜査への国民の期待が大きかったロッキード、リクルート両事件の当時と比べ、検察を取り巻く環境は変化している。ただ政界などの腐敗をえぐり出し、その実態を明らかにできるのは、特捜検察である。「巨悪に立ち向かう」伝統を持つ特捜部は、今後どのような捜査を展開していくのだろうか。
やる気のない警察官の活躍を描く:第1回警察小説大賞受賞の佐野晶さんに訊く

「ごんぞう」と呼ばれる警察官たち
警察内部の隠語で、やる気のない警察官を「ごんぞう」と呼ぶ。能力や経験があるのに働かない、自主的窓際警官だ。
警察小説というと、凶悪犯を追い詰める敏腕鬼刑事や、複雑なサイバー犯罪などをイメージするが、佐野さんの作品の舞台は、「ごんぞう」ばかりの交番。緊急配備の連絡に誰も反応せず、交通違反の取り締まりも全国最低レベルで、いつも無駄話をしながらお茶を飲んでいる。県警の幹部たちも彼らの扱いに手を焼いている。
「正直に言うと、警察小説は苦手。特に鬼刑事が登場する定型の警察小説には、あまり興味ありませんでした。私の日常生活から、とても遠い存在でイメージが浮かばない。しかし、警察組織の中でもあまり注目されない“ごんぞう”の存在を知り、交番のお巡りさんの話にしたら書けるかな、と思いました」と佐野さんは話す。自宅近くの神奈川県・湘南が現場だ。
主人公の新人警官、桐野がこの交番に配属となる。桐野は国家公務員の試験に落ち、地方公務員採用で警察官になった。女性副署長からの密命を帯びて着任する。「税金泥棒を警察からたたき出すため、(ごんぞうたちの)サボタージュの実態を記録して、報告してほしい」。“内部スパイ”の報酬は、何か月後には、国家公務員試験に再挑戦などのため、勉強時間がたっぷり取れる職場に引き上げるというものだった。
内部スパイを指示した女性副署長本作は『ゴースト アンド ポリス GAP』と長い題名だ。「ゴースト」は、初めの方に出てくる、住民からの「お化けが出る」という訴えなどに由来する。「お化けを出すと、話が転がりやすくなるので、使いました」と佐野さん。「GAP(ジーエーピーと読む)は、純粋にごんぞうに徹して生きる小貫と、それを裏切ってスパイする桐野の主人公二人のギャップも意味しています。やがて二人のギャップはだんだんと変化していきますが」
スパイを指示した女性副署長の存在も面白い。佐野さんは笑いながら、こう話す。「警察内部の“社内恋愛”は必ずばれると言われるように、警察にはスパイ的なことを指示している幹部や、それに従う内部通報者が必ずいるのだろうと想像して書きました。初めは男性の副署長を考えていたが、若い警官を籠絡(ろうらく)できるよう、魅力的で、一癖も二癖もある女性にした方が面白いだろうと思い、ある友人の浮気相手を人物イメージしてみました」
佐野さんは27歳から、テレビの脚本を書いてみようと執筆を始めた。しかし、賞の候補にはなったものの、花開くことはなかった。20年ほど前からは、映画のノベライズを中心にしている。「韓国ドラマも相当、本にしました。何日までに書け、と言われれば、絶対に守り、少し粗製乱造だったこともあるが。是枝監督作品を本にする時は、監督が時間を取ってくれて、気になったシーンの意味を尋ねると、丁寧に教えてくれました」
小説を自分で書くのは今回が初めてで、54歳(当時)にして「初作品初受賞」となった。「アンチヒーロー的な主役が魅力」「落語の世界を感じさせる、愉快で、物悲しく、人間味のあふれる警察小説に仕上がっている」「意外性が抜群で、主人公の新人警官の青春小説でもあり、成長過程を描いた成長小説にもなっている」と3選考委員の満場一致で選ばれた。新しい警察小説というテーマに、最も斬新な形でこたえたと評価されたのだ。
佐野さんは次作の構想を固めつつある。「妻が出版社にいて、『毒の本がよく売れる』などと言うので、毒をテーマにした小説にしようかと、考えています。もちろん、私が書くのは人を殺さない毒薬ですが」と、優しい人柄を感じさせる。
「今回、あまり登場しなかったごんぞう交番の面々の続編も、検討しています」。決して力まず、激しい警察小説は書かず、ごんぞうに温かな目を向ける、新タイプの作家が登場した。
【新刊紹介】最強在日ヤクザの生涯:竹中明洋著『殺しの柳川ー日韓戦後秘史』
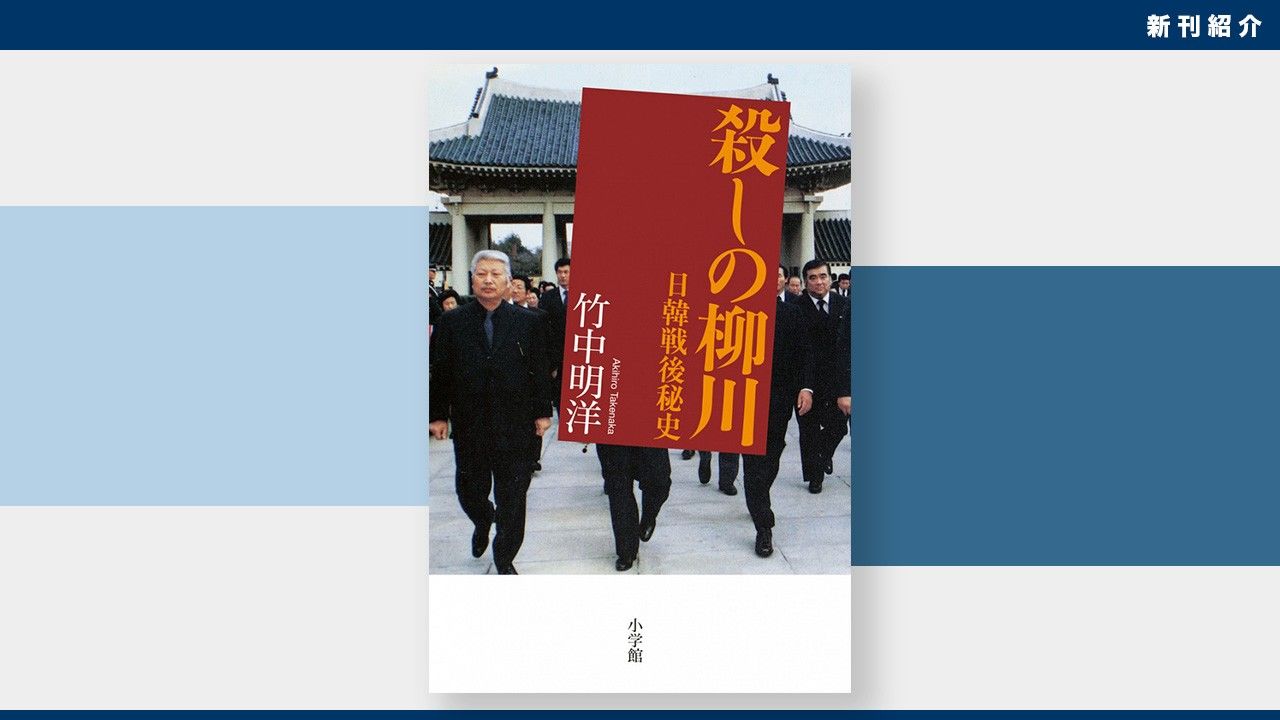
日本名、柳川次郎は1923年に釜山で生まれ、7歳で海峡を渡り、大阪で在日韓国人として生きた。最盛期には1700人の組員を抱え、全国広域5大暴力団に指定された「柳川組」の組長となり、「殺しの柳川」という異名で恐れられた。
警察の集中取り締まりで69年、組は解散に追い込まれる。この本は、元NHK、週刊紙記者の著者が、45歳で堅気になってから91年に亡くなるまでの柳川の生涯を追いかけている。柳川の関係者から丹念に証言を集め、日韓の政治家が次々と実名で登場してくるのは、実に興味深い。
柳川が組の解散を決意したのは、在日の少女の新聞投書だと言っていた。「あなたのおかげで日本にいる韓国人の中には、はずかしい思いをしている人がいっぱいいる」とあったという。しかし、著者は「美談に過ぎる」と断じ、「韓国への強制送還を(警察などから)ちらつかされたため」という説を挙げている。
金大中事件で日韓関係に亀裂が入った翌年の74年に「日韓親善友愛会」を設立。半年後に、韓国政府の招待で44年ぶりに祖国を訪れた。無類のプロレス好きだった朴正煕大統領から直々に依頼を受けると、アントニオ猪木対金一(大木金太郎)の「因縁の韓日対決」を韓国で実現。テレビ視聴率はなんと90%を上回り、各地を回った韓国興行は大成功だった。柳川は猪木、金一とともに青瓦台に招かれ、大統領は柳川をハグして感謝の気持ちを伝えたという。
朴大統領が暗殺された後、日本は韓国の新軍部実権派と親しいルートを失う。柳川は両国を頻繁に行き来して、祖国との太いパイプを築き、韓国軍の情報機関と深く関わった。特に全斗煥大統領時代には、政権中枢にまで影響力が及ぶようになる。
柳川はこれまで暴力的なイメージが強いので、日本人社会だけでなく在日社会からも白眼視されてきた。しかし、「日韓関係が柳川のような人物たちによって、水面下で支えられてきたことは事実である」と著者は最終章で記している。
エジプトの小学校に「日本式教育」、協調性など成果も
日本の「特活」で世界初の試み
「エジプト・日本教育支援パートナーシップ(EJEP)」と呼ばれるこの事業を担当する国際協力機構(JICA)によると、外国で特活が全国規模で導入されたのは、エジプトが初めて。
ピラミッドなどで知られるアラブの主要国だが、実は教育問題を抱えている。公立学校の教員の給料が低く、家庭教師の兼任や塾経営が社会問題化。学力偏重教育による児童・生徒の人格育成の欠如や、学校不足による1クラス70~80人の詰め込み教育、卒業生の就職率の低下などの多くの問題を抱え、国を挙げて教育改革に取り組んでいる。
こうした中で、エジプトのシーシ大統領は、時間を守り規律正しく、勤勉な日本人を「歩くコーラン(イスラム教の聖典)」と高く評価。アラブ諸国には「日本が先進国となったのは、教育制度が優れているから」という認識が定着しており、エジプトが日本に協力を要請した。
2016年に同大統領が訪日した際にEJEPが締結され、日本がエジプトで、保育園から大学まで日本式教育の特徴を生かした協力を行うことになった。
35の公立「エジプト日本学校」が開校
「人を育てる教育」としてエジプトが注目したのが、日本の小学校で学科授業以外に行われている特活だった。先行して公立12校で学級会などを試験的に始め、18年9月から本格的に日本式の特活や学校運営方法を取り入れた35の公立の「エジプト日本学校」を新設して開校した。
担当のJICA人間開発部基礎教育グループ、梯太郎さんによると、同じく18年9月の新学年度から、エジプト全小学校の1年生のカリキュラムに毎週45分の特活が組み込まれた。学級会、学級指導、日直の3つを行う「ミニ特活」を導入。
学級会では、行事などのテーマを児童の話し合いで決める中で、自分の意見を主張し、相手の意見も尊重できるようにしている。学級指導では、手洗いや歯磨きなどの生活指導や、あいさつ、友達を思いやる心などを身につけさせている。日直は交代で、クラスのリーダー役を経験、学級の世話も体験してもらう。こうした教育や指導は、これまで現地ではなかった。
特活の手本となるモデル校が、エジプト日本学校(EJS)だ。日本人子弟が通う日本人学校とは違い、現地の子どもが通う公立学校。ミニ特活に加えて、児童の朝自習、掃除、職員も互いの授業を参観して助言しあう校内研修や、職員会議なども取り入れている。
初めは掃除に強い反発
この中で、児童だけでなく保護者たちからも反発があり、問題となったのが教室などの掃除だった。現地では、掃除は社会階層の低い人の仕事とされ、初めはやりたがらない子も。「掃除をやらせるために、子どもをEJSに通わせているのではない」と怒る親もいたという。しかし、児童は友達が掃除している姿を見て加わり、自分たちが使う場所はみんなできれいにする習慣がつき始めてきた。自分の机も、自分できれいにするようになってきた。
JICAの教育の専門家らが、各校を巡回しながらアドバイスを続けている。また、これまでに校長や特活を指導する教員ら計42人を日本に招き、1カ月の研修を行い、“本場”の日本式教育を学んでもらった。今後も4年程度を目安に約700人の教員らを招く予定だ。
EJSはスタートして間もないが、早くも成果が出ている。①自己主張の強い人が少なくないエジプトだが、他の児童の話をよく聞き、他の人の意見を尊重するようになった②遅刻する児童が減り、校内のケンカも減った③家で掃除や、手伝いをする子が増えてきた――。
ただ、EJSは公立校なのに授業料が高いという問題がある。校舎は新しく、一クラス35~40人で、他の公立校の半分ぐらいと、環境はいい。しかし、年間の学費は日本円で6~7万円で、一般的な学校の5~10倍にもなる。
「EJSに特別な入学試験はないが、高所得者の子弟しか通えない学校にしないでほしいと、日本側はエジプトにお願いしている。奨学金制度の拡大も求めている。日本式教育の希望者が入りやすい公立学校であってほしい」(JICAの梯さん)
人材育成に期待するエジプト
カーメル駐日エジプト大使はEJSについて、「日本の経験から学び、エジプト社会の進歩と、教育分野の包括的な改革を目指すもの。教室や小学校を小さな社会とみなし、この社会を通じて児童に道徳心を植え付け、人格形成などに役立つと願っている」と期待している。
また、EJEPなどで両国の橋渡し役を務めたヒラール元エジプト高等教育・科学技術大臣は、「今、エジプトにとって一番重要なのは質の高い人材育成だが、現在の教育では難しかった。特活など日本式教育の特徴を生かしながら、少しでも教育環境が改善されることを願っている。そうして将来、社会を担う人材が育ち、この国を引っ張ってもらいたい」と述べている。
天皇退位の本義:皇室制度の修正課題に取り組まれた新上皇

平成の皇室トップニュースだった退位
平成の始まる瞬間を30年前、筆者は皇居・宮内庁内で迎えたが、その平成が天皇の退位で終わるとは全く予想できなかった。昨年秋の読売新聞の世論調査によると、「平成を象徴する国内の出来事」上位10項目の中で皇室関連のトップは「天皇退位特例法成立」だった。天皇の生前退位を特例という形で認めたもので、退位が国民にとっていかに衝撃的なことだったかがよく分かる。
天皇退位に関する規定は、2017年に上記の特例法ができるまでなかった。そのため、戦後の国会では何度か、天皇退位に関する論議があった。政府・宮内庁は、①退位を認めると、日本の歴史を見ても院政のように、上皇や法皇の存在が弊害になる②天皇の自由意思ではない退位の強制があり得る③天皇が勝手気ままに退位できるようになる――と退位を認めない理由を説明してきた。こうした点からも、譲位・退位は好ましくないものと考える国民も少なくなかった。
しかし、平成の陛下は在位28年目の2016年8月、皇太子に譲位したい意向を映像メッセージで伝えられた。広く国民に向け、メディアを通して理解を求めるお言葉だったので、「平成の玉音放送」とも言われた。これまでの政府・宮内庁の国会答弁とは異なることを、陛下自らが話されたので、戸惑いを感じる人も多かったはずだ。
説得力があった「平成の玉音放送」
それでも、陛下の象徴天皇として国民に寄り添った実績に基づくお言葉には、十分な説得力があった。「(当時82歳で)次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています」「天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます」「我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、(中略)象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、私の気持ちをお話しいたしました」
陛下がこのお言葉の中で、「憲法の下(もと)、天皇は国政に関する権能は有しません」と述べている。この映像メッセージが法改正や新法制定の契機となり、憲法違反と受け止められないかと、ご自身も懸念されていた。だが、国民のためにこそ、終身の天皇を続けるのではなく譲位したいのだというお考えは支持された。新聞各紙の世論調査でも、今回の退位と新天皇の即位は9割前後の圧倒的な賛意が示された。
明治期に削除された「退位」
陛下は在位30年の間に、被災地への訪問や、戦没者の慰霊など、「行動する天皇」として象徴天皇の務めを果たしてきた。また、過剰警備の改善などにも心を砕かれた。様々な問題や改革に取り組まれ、最後の課題が皇室制度の見直しだったと、筆者は思う。先の映像メッセージの初めの方には、「天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います」とある。
陛下は常々、「伝統的な天皇像は、政治への関わりが少なく、国民のために務めを果たす『象徴天皇』の姿ではないか」と述べられてきた。逆に伝統的ではなかったのが、明治維新後の近代化を急ぐ中で、天皇がかつてない権力を持つことになった時代である。その明治中期の大日本帝国憲法・旧皇室典範の制定の過程で、従来の皇室制度から外された最たるものの一つが「譲位」だった。
当時、譲位を認める案も検討されたが、初代首相だった伊藤博文の反対で旧皇室典範の条文から削除された。天皇が実権を握った者に退位させられたり、皇室が分裂して乱れの原因となったりして、近代国家となった日本が不安定になることを恐れたからで、「天皇が不治の重患になったら、(天皇の代わりを務める)摂政を置けばよい」というのが伊藤の考えだ。こうして、天皇の退位規定が設けられなくなり、終身在位の天皇制が誕生した。
これに基づき、大正天皇が重病となった時に、皇太子(昭和天皇)が摂政を5年間務めることになった。この前例に従い多くの国民は、天皇が高齢で動けなくなったら、摂政に任せればよいのでは、と信じ込んでしまってきた。
ご自分でしか解決できない課題への挑戦
戦後の憲法で、天皇は政治権力のない「象徴」となり、本来の姿に戻ったが、皇室制度、そして国の根幹に関わる皇位継承の退位の問題が残されていた。しかし、戦後しばらくの間は、昭和天皇退位論の問題があり、退位を議論するのは敬遠された。年月を経て、退位は政治家も国民も言い出しにくくなっていく中で、陛下は在位とお年を重ねるうちに、この問題を解決できるのはご自身であることに気付かれた。そのため、異例の国民に直接話しかける形をとられたのだと、筆者は思う。
先の映像メッセージの中で、摂政を置くことについて、「天皇が十分に(中略)務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりありません」と、否定的な見解を述べている。天皇はただ存在するだけでは意味がなく、在位中は国民のために力の限り務めを果たし続け、それが出来なくなったら皇位を譲るべき、というご自分で考え抜いた「象徴」の在り方を貫かれたのだ。こうした深い思いから、長い天皇の歴史の中で異質だった終身在位の決まりは消えることになった。
葬儀改革も決断
退位問題の前に、陛下はもう一つの改革を行っている。映像メッセージの3年前(2013年)、宮内庁は両陛下のお気持ちを表した「今後の陵と葬儀のあり方」を公表した。①お二人の陵を寄り添う形に造り、従来の天皇、皇后陵より敷地面積を縮小する②陵の簡素化の観点からも、火葬にする――という葬儀改革だった。
特に天皇の火葬は国民を大いに驚かせた。「今の社会では火葬が一般化しており、歴史的にも天皇皇后の葬送は、土葬、火葬のどちらも行われてきた」という説明だった。ご葬儀については、これも天皇ご自身でしか言い出せず、決断できない改革で、根底に国民の負担や影響を少なくしたいというお考えがあるのは言うまでもない。
「天皇の最大のお務めは、先帝から受け継いだ皇位を、きちんと次の天皇にお渡しすること」と、筆者は昭和天皇に長く仕えた侍従に教えてもらったことがある。ごく当たり前のことだが、それが「世界最古の皇室」を守っていく極意なのだと悟った。歴史上、退位は125代天皇の新上皇が59例目になる。歴代天皇の半数が譲位してきた事実からも、生前の退位は、若干の例外があったとしても、次の天皇への継承を確実にする極めて有効な制度だったのだ。
令和の時代に入り、誰も目にしたことのない上皇の在り方を見せていただきたいと願う国民も多いだろう。また負担をおかけすることになるが、それが次の務めであることは、202年ぶりの上皇さまは十分に分かっていらっしゃると、筆者は確信している。
【書評】名評論家からの老いへの指針:草柳大蔵著『ひとは生きてきたようにしか死なない』
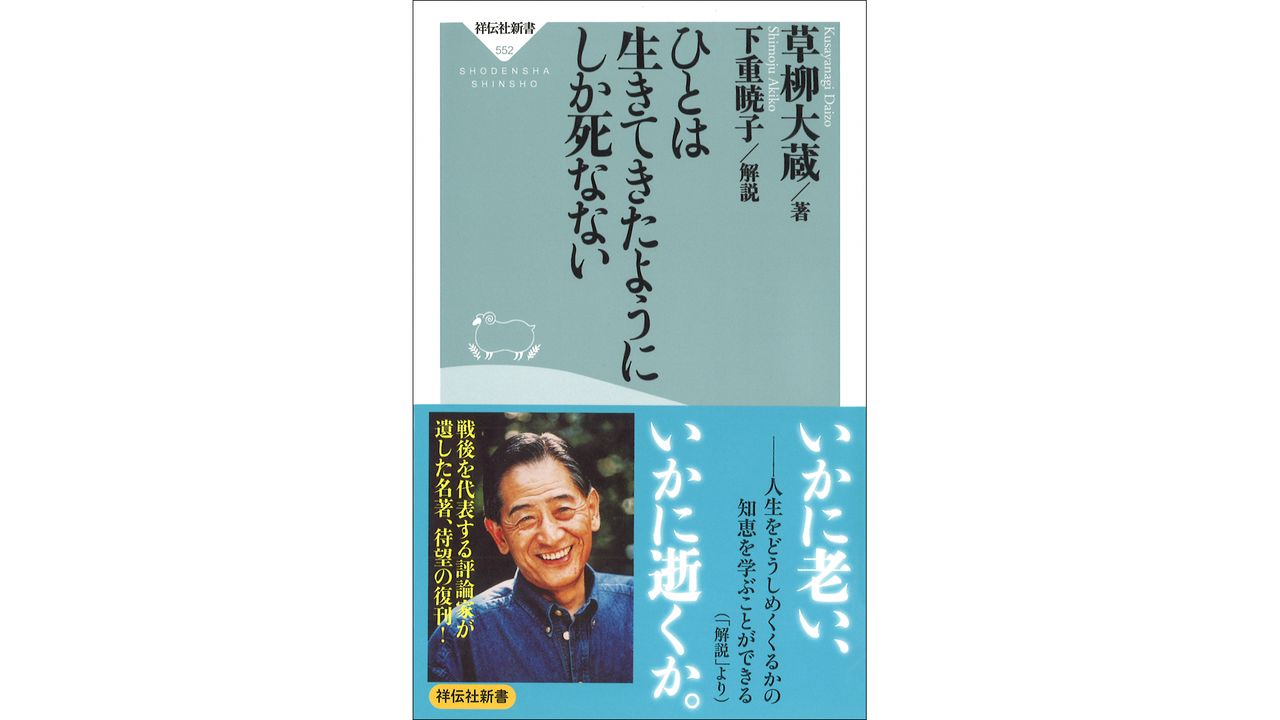
20年の経過を感じない復刊本
草柳は東大入学後すぐに学徒出陣し、特攻隊員を志願。出版社や新聞記者を経て、ジャーナリストの大宅壮一に師事し、「週刊新潮」や「女性自身」の創刊に参画した。敗戦まで日本最大と言われた頭脳集団を3年にわたる取材で描いた『実録 満鉄調査部』や文藝春秋読者賞を受けた『現代王国論』など、ノンフィクション作家としても活躍。礼儀作法や女性論など幅広い分野で書き続け、2002年に78歳で亡くなった。
本書『ひとは生きてきたようにしか死なない』は1999年に刊行された。今回の復刊本を読んでも、20年たっているのに全く古さを感じさせない。昨今売れている「老い」に関する多くの書籍を先取りし、本質を捉えているからだ。
舞台の花道を一人で進む老年者
冒頭で、老年者を歌舞伎の花道にさしかかる役者に例えている。本舞台の幕は引かれ、主人公は戻ることはできず、残された道は一筋。「在りし日へのほほ笑みと、過ぎしことへの慚愧(ざんき)の念を全身に秘めて黙って歩むほかはない。(中略)おのれの花道の足取りにゆるぎのないことを願うのみである。本書はその思いで書いた」。本の題名の意味が、なんとなく分かってくる。
ドイツの文豪ヘルマン・ヘッセの老人論『人は成熟するにつれて若くなる』の一節が紹介されている。「老年が青年を演じようとするときにのみ、老年は卑しいものとなる」。青年よりずっと自由に寛大に、自分自身の愛する能力と付き合えばよい。ヘッセは私たちに「老人の美学」を贈ってくれたのだと、草柳は記している。
本書は5章25節からなるが、「老人にさせられる」と題した節は特に興味深い。「老人は『老人』と言われるのを嫌う。『老人扱い』はもっと老人を傷つける」。そして、『ガリバー旅行記』の著者スウィフトの名言が紹介される。「誰でも長生きしたいと願うが、年をとりたいと願う人はいない」。草柳は「人間は、『私はまだ老人じゃない』と言い張っていても、『老人になる』よりも『老人にさせられる』のである」と述べている。
続いて北極圏のアラスカ・インディアンの棄老(きろう)伝説が出てくる。最低気温マイナス57度の厳冬を乗り切るため、集団のリーダーから「おいていく」と告げられた80歳と、少し年下の老女。二人だけで知恵を絞りながら生き延びた後、老女たちは「なぜ集団から棄(す)てられたか」を考える。
「あたしらには長い人生で身につけたことがいっぱいある」
「あたしらがあんまり長いこと、自分たちはもう無力だ、なんて若い者に思わせるようなことをしてきたから、若い者のほうも、あのふたりはもうこの世の役に立たない、と思い込んでしまったんだよ」
そして二人は、こう決意したのだった。
「とことん闘って死んでやろうじゃないか」
「私の中の老い」と「老いの中の私」
草柳は「私自身が70歳を超えて思うのは、『私の中の老い』と『老いの中の私』の二つの姿である」と書いている。「足し算の老後」について、「『私の中の老い』を自覚しながらも、『老いの中の私』に、もうひと花咲かせてみようと考える。『老い』とは、人生の持ち時間の少ないことである。少なければ少ないだけ、今まで『やってみたい』と思ったが、仕事や生活の関係でやれなかった、それを今思い切って『やってみる』のである」と説明している。
本書は参考になる健康法についても、たっぷり書かれている。「健康法というのは人それぞれであるべきだが、その健康法が効力を発揮するのは『継続』という時間の力が大きく寄与するのではないか」
草柳本人が16年間続けていたのは速歩(そくほ)術。簡単なルールは(1)速度は1分間80m以上で、行進曲で歩く時のスピード(2)40分間、休みなしで(3)背筋を伸ばし、かかとから着地。このウオーキングを1日おきにやっていた。
徳川家康の懐刀で、100歳を超える長寿だったといわれる僧、天海の人生の過ごし方が紹介されている。「気は長く、勤めは固く、色うすく、食細うして、心広かれ」。天海は家康に「時々、ご下風(かふう=おなら)のこと」とすすめていた、と記している。
今の時代を先取りした本書
老いに関する著書が多く『家族という病』『極上の孤独』などの作品で知られる、作家で評論家の下重暁子さんが、復刊本の終わりに解説でこう書いている。
「人生百年時代を迎え、老後の生き方が焦点になる。今の時代を先取りしたかのような本書の中に、その答えがある。(中略)生きてまた道程の先の集大成、人生をどうしめくくるかの知恵を学ぶことができる」
草柳の長男、力重さん(67)は「父が亡くなる3年前に書いた作品を復刊していただき、感謝しています。年齢が近くなり、父がぼんやりと死を意識しながら、日本人へのメッセージを残そうと書いたのがわかる。高齢者がどんどん増える今日、絶好のタイミングで復刊されたので、改めて多くの方に読んでいただけたら、ありがたい」と話している。
